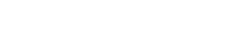節約のためファイナンシャルプランを立てよう
広告
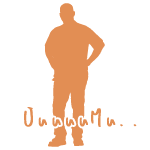
子供が生まれたら、今までよりお金がかかる。多くの家庭では節約を考える。我が家ももちろん節約節約。子供と家族の将来のため貯金も必要。
節約や貯金を考える際に大事になるのがファイナンシャルプラン。これが無いと家計簿を見ても、何を削るべきかみえてこない。
ファイナンシャルプランを簡単に作成しよう、今回はそんなお話。
フィナンシャルプランのエクセルシートをver.3にリニューアルしました(2011年2月3日)
お金の計画・ファイナンシャルプラン立ててます?
子供が生まれる以前から家計簿はつけてきた。ざっくりとだが。しかし家計簿をつけていて疑問が
「ずっと記録してるけど、記録しているだけでなんの役に立っているのだろう?」
そう、家計簿をつけていても記録を後々振り返られるというだけで、現状のお金の管理に役立っていない。子供が生まれたからには、子供のため、家族のため計画的な貯金が必要。そして可能な限り無駄な出費を抑えて将来に備えなければならない。このままではいかん。
そう、将来のため、現在はどこまで使ってよいのかという目安が無いと家計をつけていても無意味だ。よし、そうなれば目安となる数字を決めたファイナンシャルプランを作ろう。
家計の各項目(費目)の支出目安
| 項目 (費目) | 月間手取り額に対する 支出割合 | 内訳 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 貯蓄 | 10% | 貯金・子供保険・子供積立・個人年金 | 自営業は15%以上 年俸制でボーナスが無い場合は15% 子供の積み立ては毎月1万円 |
| 保険料 | 8% | 夫婦の生命保険・自動車保険 | 上限10%、下限8%だが、下げれる場合も 家計節約・保険料を安くしようで解説 |
| お小遣い | 8% | 夫婦のお小遣い | |
| 住居費 | 22% | 家賃・ローン | |
| 教育費 | 4% | 習い事・子供の教育施設 | |
| 光熱費 | 7% | 電気・ガス・水道 | |
| 通信費 | 5% | 固定電話・携帯電話・インターネット・郵便 | 7%が上限 |
| 交通費 | 2% | ガソリン・有料道路・電車・バス | |
| 自動車関連 | 2% | 自動車維持費・自転車 | |
| 食費 | 13% | 食費・外食費 | 下限は無いが、やりすぎると寂しい食卓に |
| 被服費 | 3% | 大人の衣服 | |
| 家具・生活用品 | 3% | 家具・雑貨 | |
| 医療・衛生 | 3% | 治療費・医薬品・衛生消耗品 | |
| 子供費 | 5% | 子供に関わる物への出費 | 2人いる場合は8% 上が幼稚園児なら2人で12% |
| 教養・娯楽 | 2% | 書籍・音楽関連など | |
| 交際費 | 2% | 贈答品など | |
| 予備費 | 1% | 急な出費に備えて |
ポイントは貯金
上記の表が基本的な支出の目安。ただこれは各家の状況によって割合は変わる。野菜がもらえる環境なら食費は下がるし、田舎と都会では交通費も異なる。
どうしても守りたいのが貯金。10%の貯金を確保することが最重要。ボーナスは貯金しよう。そのため、ボーナスなどの賞与が無い仕事の場合は月々の貯蓄は15%や20%と高めの設定にしよう。
貯金の割合を保ったまま、後の数字はそれぞれの状況に応じてベストな割合に調整すると良いだろう。
ちなみに私の会社は交通費が出ないので、交通費の割合がとんでもなく大きい・・(T_T)。
貯金の額や節約必要額をもっとはっきりつかむために、ライフプランの作成も効果的だ。詳しくは貯金のコツ、資金計画・ライフプランを作ろうで。
大切なのは家計簿との連携
日々の支出を家計簿ソフトで記録・管理して、記録が完了した月のデータを上記のエクセルデータに入れて収支のバランスを確認する。
なので、まずは家計簿をつけなくてはならない。
- 家計簿なんて面倒でつけてられない
- 家計簿ソフトってたくさんあって、何を使えばいいのやら・・
・・・最近はレシートから自動で家計簿を作ってくれる便利グッズもある。
家計簿ソフトもフリーソフトで十分使えるものもあるし。。。
家計簿自動作成やおすすめフリーソフトについては簡単に家計簿を作成。レシートから自動入力にて。
エクセルデータのダウンロードと使い方
上記の表のエクセルデータを用意したので、ほしい方はどうぞ。
以前のものからバージョンアップした。以前のものより使いやすくなっているはず・・。
ファイナンシャルプラン ver.3(Excel)のダウンロード
- ver.2:変更点多数ありすぎ。ver.2からが正式版。ver.1は使いづらいのでやめましょう。
- ver.3:ver.2の分類・支出割合などのミスを訂正
エクセルデータの使い方
このエクセルデータは、薄い黄色が塗られているセルに数値が入力するように作成してある。(それ以外のセルは基本的に計算式が入っているので変更する必要なし)
- 2行目に毎月定期的に入る収入の手取り額を入力。変動する人は、おおよその値を入れる。
- するとE列72行目に収入の合計値が出る。これが計算の元になる。
- 次に予算の設定。C列にはこのページで紹介した項目ごとに支出割合が入力されている。これを元に、D列に実情にあった支出額になるように修正した支出割合を入力する。E列には入力した支出割合と収入の合計から割り出された予算額が表示される。
- ここまでで予算の設定は完了。つぎは実際の支出と収入を入力していく。
- 1月など、各月で薄い黄色が塗られているセルに各項目ごとの支出額を入力していく。貯蓄や保険料などはさらに小項目になっており、小項目を入力すると合計額が出るようにしてある。(内訳が見えたほうが、節約や契約内容の見直しに役立つと思われるものに対して小項目を作成してある)
- 入力された値が予算額を超えた場合はピンクで表示される。
- 貯蓄だけは値を超えたほうが望ましいので、ほかとは逆に予算に満たない場合はピンクで表示される。予算を超えた場合は青で表示。
- 支出の入力を終えたら次は収入。67行目から71行目に、給与・休業手当(共働きなら夫婦の合計額)、子供手当てなどを入力。金額は必ず手取りを入力。
入力上の注意点は、67行目の”給与・休業手当”は必ず入力すること。平均値などを割り出す計算式がこの67行目を参照しているので、ここを入力しないと後の”月平均”、”予算-累計”などが計算されない。
支出を入力した月は必ずここに値を入れよう(収入無なら0円と入力)。支出も収入も無い場合は空欄でよい。(例:4月から入力し始める場合、1月から3月までは空欄) - ここまでの入力を終えると、収入の合計額(72行目)から支出の合計額(66行目)を差し引いた値、残金(73行目)が算出される。
- R列には入力月の平均値が表示される。この平均値と予算額がかけ離れている場合は、D列の修正割合の値を修正して予算配分を見直そう。
- S列には入力つきの合計値が表示される。12ヶ月入力すれば各項目(費目)の年間使用額、年間貯蓄額がわかる。
- T列には入力月までの累計予算から、実際の累計を引いた値が表示される。
例えば、4月から8月までの5ヶ月間入力した場合、(5か月分の予算)?(4月~8月までの支出)が出る。
ここがピンクになっている項目は当月までの予算を使用金額が上回っているということなので、次月での節約を意識しよう。
月ごとに[手取り金額×支出割合]としてたほうが正確なのかもしれないが、収入があるまで支出の目安がわからないのも困ると思い、毎月一律の計算となるようにしている。ただそれだけでは、実際の収入に対して支出が多かったどうかわからないので、月の収入と支出の差額がわかるように67行目以降の計算を用意した。
ver.2から固定費と変動費に分けて表示してある。どちらも節約できるものだが、変動費のほうが節約しやすい。(固定費でもお小遣いは節約しやすいけどね。お小遣い無しにすればいいだけだから・・・orz)
項目の並び順は、簡単な家計簿作成方法で紹介したフリーソフト、うきうき家計簿に合わせてあるので、
うきうき家計簿で日々の支出を入力したら、
”テキストデータ出力”でデータを出力して、
あとは上から順にデータを貼り付けていけば完成する。(固定費・変動費に分けたので、並び順は完全には一致しない)
フィナンシャルプランの活用方法
せっかく作ったフィナンシャルプラン。これを使って上手に家計を管理して節約しよう。
- 貯蓄ができている上で残金がプラスであればその月は黒字。残金は使ってしまっても良いし、もちろん貯金しても良い。この”いくらまでなら使っても良いのか見える”という安心感は大きい。
- T列の”予算?累計”がピンク(赤字)の項目は要注意。次月からの節約を意識しよう。
- 最重要は貯蓄。これが確保できているのならほかは赤字でも良い。残金が赤字では意味無いけどね。┐(´ー`)┌
- 支出の割合を見直す場合は、貯蓄以外の値を見直そう。貯蓄10%は死守。
貯蓄ができていて黒字ならあまり細かいことは気にする必要は無い。
入力の所要時間は30分ほど
長々と書いてきたので面倒そうに見えるが、やってみると案外簡単。
私は、家計簿の入力は2週間に1回くらいでまとめて入力している。30分もかからない。
そして翌月にフィナンシャルプランのエクセルシートに入力。これも15分ほどで終わる。
何が大変かといえば、フィナンシャルプランのエクセルシートを作るのが大変だった。。。orz。
このシートがある今、大変なことはもう無い。貯金が増える簡単節約術・書くだけ節約に書いたとおり、つけ始めるとお金がたまりだすから、本当にお勧め。