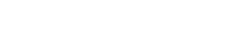生命保険・個人年金控除・減税の仕組みと金額
広告

減税と育休で保育料を安く引き下げようでも書いたが、減税を活用することで、所得税が返ってきて、住民税は安くなり、保育料まで安くなる。
活用しない手は無い。
そんなわけで生命保険料控除・減税の仕組みを知って、お得に節約しよう。今回はそんな話。
*所得控除の仕組みが変わりました。この記事は旧生命保険料に基づく計算です。新生命保険の計算はまた別の記事で書きます。
生命保険の控除による減税の仕組みと金額
子供が生まれたのに生命保険に入っていないというのは絶対に避けなければならない。必ず入ろう。保険料の目安は収入により異なるが、月収の8%前後とよく言われる。ただし、最近は保険料の安いネット生命保険も誕生したので、一概に8%とは言い切れない。どれくらいが適正なのか、プロに相談したほうが早い。
それ以外の目安として、「保険金は安くてよいので、最低年間10万円を少し超える保険料を納める」というのもある。これは控除額を考えてのこと。(一般的に生命保険は年10万円を超える)
生命保険料控除は所得税・住民税が安くなる仕組みなのだが、10万円越えが最も控除額が多い。詳しく見てみよう。
| 年間の支払い保険料 | 控除される金額 |
|---|---|
| 2万5千円以下 | 年間に支払った保険料全額 |
| 2万5千円超~5万円以下 | (年間の支払い保険料×1/2)+12,500円 |
| 5万円超~10万円以下 | (年間の支払い保険料×1/4)+25,000円 |
| 10万円を超える場合 | 一律5万円 |
年間10万円超の保険料を納めていれば、年末調整時の申請で年間所得から10万円引いた額で所得税を再計算してくれるわけだ(´∇`)。収入が10万円少ないから納税額も少なくしてね、ということ。
(*勤め人の場合は毎月会社が徴収しているので、そこから返ってくる。個人の場合は納税額が減る。)
次に住民税を見てみよう。
| 年間の支払い保険料 | 控除される金額 |
|---|---|
| 1万5千円以下 | 年間に支払った保険料全額 |
| 1万5千円超~4万円以下 | (年間の支払い保険料×1/2)+7,500円 |
| 4万円超~7万円以下 | (年間の支払い保険料×1/4)+17,500円 |
| 7万円を超える場合 | 一律3万5千円 |
年間10万円を超える保険料を納めていれば、翌年の住民税額は所得が3万5千円引かれた形で計算される(´∇`)。
現金が戻ってくるわけじゃないので、「お金がもらえる、やったー」という盛り上がりが無いのがちょっとさみしい(・ω・)。住民税は前年の所得を元に計算されるのでこうなる。戻ってくるより徴収されないことのほうが、手元現金が減らないので得なんだけどね。
生命保険を年間10万円納めれば、所得税控除と住民税控除で合計8万5000円、所得が低く計算される。
で、どれだけ節税できるか?
それを出すのはまだ早い。次の個人年金控除も見たあとで計算しよう。
個人年金の控除による減税の仕組みと金額
生命保険は入っているが、個人年金はまだ、という人も多い。しかしこれは非常にもったいないので是非加入しよう。
個人年金は普通の年金同様、お金を納め続けるとある年齢から年金が受け取れるというもの。
- 「これ以上年金納めたくないよ」
- 「老後よりも今が大事。早死にするかもしれないし」
なんて思う人もいるが、とんでもない。収めないなんて大損(>◇<)
メリットは
- 所得税控除の対象になる
- 住民控除の対象になる
- 普通預金より利率がいい
- 解約時には納めたお金が戻ってくるので損が無い
1、2は後述するのでまずは3の利率。会社や種類によって変わるが、保険会社が運営する個人年金のプランの多くは普通預金より利率がよ伊野が普通。貯金する予定のお金があれば個人年金に回したほうがお得である。
4の戻ってくるは契約時に確認が必要だが、通常の貯蓄型プランであれば解約すると納めたお金は戻ってくる。もし生活が苦しくなって解約しても損は無いのだ(・∀・)ノ
3、4から、個人年金のデメリットは「手元現金が減るでしょ」ということだけになる。しかしここは減税が助けてくれる。
生命保険同様、生命保険会社などが運営する個人年金も減税の対象となる。こちらも計算は生命保険と同じ。
| 年間の支払い年金料 | 控除される金額 |
|---|---|
| 2万5千円以下 | 年間に支払った年金料全額 |
| 2万5千円超~5万円以下 | (年間の支払い年金料×1/2)+12,500円 |
| 5万円超~10万円以下 | (年間の支払い年金料×1/4)+25,000円 |
| 10万円を超える場合 | 一律5万円 |
住民税も生命保険度同じで、
| 年間の支払い年金料 | 控除される金額 |
|---|---|
| 1万5千円以下 | 年間に支払った年金料全額 |
| 1万5千円超~4万円以下 | (年間の支払い年金料×1/2)+7,500円 |
| 4万円超~7万円以下 | (年間の支払い年金料×1/4)+17,500円 |
| 7万円を超える場合 | 一律3万5千円 |
このとおり、減税額と払い込み金額の関係は生命保険と同じ。
保険と違って戻ってくるお金なので、こちらのほうがお得感がある。
ただし、個人年金は所得税控除の対象になるものとならないものがある。くわしくは保険屋さんに相談しよう。
生命保険・個人年金で5万円の減税+保育料節約
上記のとおり、生命保険料の控除で年間8万5000円、個人年金の控除で年間8万5000円。合計で17万円も課税所得が安くなる。
それで実質、いくらぐらい得するのか?
- 年収400万円で計算してみると納税額の合計はおよそ90万4000円
- 17万円引いた383万円のときの納税額の合計はおよそ85万4000円
なんと減税だけでも5万円もお得!
減税だけでもとしたのはわけがあって、保育料金は控除後の所得で計算されるので
保育料も安くなる
そう、保育園などを利用している人は5万円以上の節約なのだ。
「生命保険は必要だから入るけど、個人年金は・・」
という人が結構いる。もったいない。所得税を納めているのなら生命保険と個人年金の両方に入ろう。
子供のために学資保険に入ることも考えるが、学資保険は利率のいい貯金。減税などのメリットは無い。生命保険・個人年金にも加入して、毎月貯金もできているのなら学資保険に加入するメリットはある。
貯金も苦しい中で学資保険に入ってしまうと、自由に動かすことができるお金が無くなり、何かあったときに非常に危険。生命保険・個人年金も年間10万円を越える部分は、無理し過ぎないように。手元資金を大事にしよう。
動かせるお金のこと指して流動性のある資金と表現する。流動性のある資金を持つということは、個人でも企業でもとっても大事なこと。だからみんな現金払いが一番うれしい。
独身のころは私の資金は流動性がとても高くて、どんどん流れ出ていったなー(´Д`。)
節税で生まれた流動性のあるお金は、ちゃんと器(銀行)に入れておこう・◇・)ハイッ!!